開催報告

令和2年(2020年)1月17日(金)、東京・千代田区のUDXカンファレンスで、セコム財団40周年記念シンポジウム「AI時代の新しい医学の挑戦 -保健医療分野のデジタルトランスフォーメーションを目指して-」が開催されました。
本シンポジウムは、セコム財団が平成29年度より特定領域研究助成・先端医学分野で実施している「多階層医学プラットフォームの構築」(領域代表者 桜田一洋/共同代表者 古関明彦)の普及啓発を目的として開催されたもので、大学や研究機関の医学系研究者のみならず、民間企業の方々も数多く、当日は90名以上の参加がありました。
目﨑祐史・セコム財団代表理事より開会の挨拶があり、シンポジウムが始まりました。
最初に、領域代表者である桜田一洋先生(理化学研究所)から、領域の背景や本シンポジウムの狙いについて紹介がありました。
近年は個別化医療から、さらに個別化予防にシフトしてきましたが、人は一人ひとり違っており、また健康な時から時間をかけて次第に病気になっていくという“becoming”の視点で考えていくことが大事であると強調されました。そして、この“becoming”を捉えるためには、従来のようにメカニズムで理解しようとする方法では限界があり、生命を非線形動的システムとして捉えてPhenotype全体を解釈するという視点の転換が必要であるとの話がありました。

桜田一洋先生
次に、共同代表者である古関明彦先生(理化学研究所)が「複雑な病気を単純なものとして捉えることができるか?」と題して、基調講演を行いました。人が病気になるのは非常に難解なプロセスであり、体にとっての本当のストレスや、人それぞれの生活履歴もほとんどわからない中で、同じ病気の方々の中に共通のルールを見出すこと(層別化すること)はほとんど不可能に近い。その例として、原因も発症年齢も様々で、標準的な治療法が効く人も限られるというアトピー性皮膚炎についての研究紹介がありました。
マウスによる実験結果を人間に外挿するためには、人間のデータ取得が不可欠です。そこで300名程度の患者の方々から継続的な協力を得て、皮膚の状態や遺伝子発現パターンなどを調べながら、それらのデータの統合を試みました。その結果、IL33や好塩基球に加えてPTN(仮称)が重要なバイオマーカーであることがわかり、病気のモデルをさらに詳しく解明することができたと講演を締めくくりました。
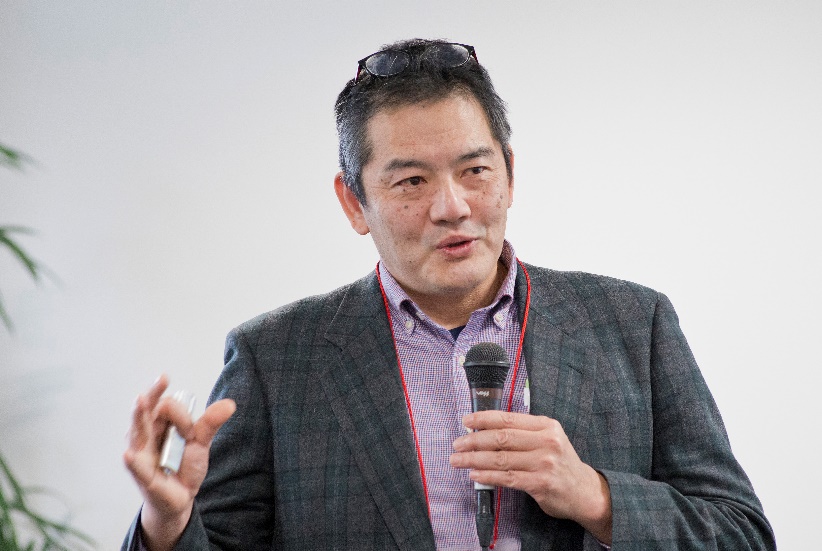
古関明彦先生
その後、川上英良先生(理化学研究所)が「予防・個別化医療に向けた時系列マルチモーダルデータに基づく状態遷移予測モデル構築」と題して、講演を行いました。個別化医療の実現に向け疾患状態を定義し、その定義に基づく疾患進行をモデル化する研究について紹介がありました。
従来、手術をしなければわからなかった卵巣腫瘍の状態について、手術前の血液検査データのみから機械学習によって新しい医学的な分類を見つけることができました。単に学習させるデータを増やせば新しいパラメータを発見できるわけではなく、臨床的な課題とリンクさせて分類していくことが重要です。また、時間変化を見るためにエピジェネティックランドスケープという状態パラメータを二値化し、さらに高頻度に発生するケースを谷として地形図のように表現する手法を使い、日本最大規模の健診データを分析することで、糖尿病などの疾患の発症過程をモデル化する研究も行っています。AIの説明性を高めることの重要性や、クオリティの高いデータを持続可能な形で収集して、常にシステムをアップデートしていくことが重要であると語られました。

川上英良先生
後半は、パネルディスカッション「AIを駆使して病気のリアリティーに迫る ~新しい科学が拓く地平~」が行われました。桜田先生がモデレーターを務め、古関明彦先生(理化学研究所)、合原一幸先生(東京大学)、垣見和宏先生(東京大学)、川上英良先生(理化学研究所)、岩見真吾先生(九州大学)がパネラーとして登壇しました。
最初に合原一幸先生(東京大学)が「未病の科学」と題して講演されました。未病を数学的に定義し、もうすぐ病気になることが発症前にわかる手法について話がありました。
従来の静的バイオマーカーでは、病気状態と健康状態を識別できるだけでしたが、動的ネットワークバイオマーカー(DNB)を使うことで、疾病前の状態を定義できます。ここではその“揺らぎ”が臨界状態では大きくゆっくり揺らぐことから、もうすぐ健康状態から病気状態への状態遷移が起こることがわかるようになります。これを数学的に定義するために、非線形システムの分岐構造は典型的には5つしかないことを利用します。疾病前状態では部分ネットワークが揺らぎます。また発病のときは揺らぎの相関係数が+1から-1の間に収束します。このことからDNBの揺らぎの標準偏差の平均値と、DNBの要素間の揺らぎの相関係数の絶対値の平均値を組み合わせると、発病が近づくとその値が急に大きくなることがわかり、未病状態を数学的に定義することができました。ただし、進行の過程で分岐が発生している場合にのみ適用可能です。数学の理論は応用が広いことが強みであり、医者が高額治療を継続すべきかを判断する際に適用して医療費を抑えることや、さらには電力システムが不安定化しブラックアウトが起こる前にその予兆を検知すること、道路の渋滞が発生する前にその予兆を検知するような応用も考えられるなど、社会問題解決への貢献の可能性についても話がありました。

合原一幸先生
次に垣見和宏先生(東京大学)が「がんの多様性に挑む ~イムノグラムを用いたがん免疫治療の個別化と複合化~」と題して講演されました。臨床医の立場から、癌の免疫治療を例として、AIを使った最新研究と現場との間に大きな谷間があることや、AIを使った研究への期待が高いことについて話がありました。
癌の免疫治療は、体の中にある腫瘍免疫という癌細胞を殺す細胞を活性化して治療します。しかし、その仕組みは非常に複雑でダイナミックであり、癌細胞を殺すのを邪魔するマクロファージが存在し、PD-L1という免疫を邪魔する抑制分子が発現することがあります。これからの癌治療に求められているのは、一人ひとりの個別化です。次世代シーケンサーを使い腫瘍の中の遺伝子情報を見て、免疫の状態をグラフで表現すると、人ごとに全く異なるグラフが出来上がります。体の中の様々な代謝や腸内細菌の影響など、情報がとても増えることから、AIの力が必要となってきます。免疫には様々なステップがあり、川上先生や合原先生の力を借りてモデル化して解決できることを期待しています。データは少しずつ蓄積していますが、人材不足という大きな谷間がありますので、多くのAIの先生方のお力を貸して頂きたいという話がありました。

垣見和宏先生
次に岩見真吾先生(九州大学)が「数理モデル型の定量的データ解析との融合」と題して講演されました。最近はモデルを作ってシミュレーションを行う数理モデル型のアプローチと、機械学習などに代表されるデータドリブン型アプローチが存在しますが、両者は敵対するものではなく、融合させようと挑戦されている話がありました。
臨床の現場からハイスループットなデータを得ることは簡単なことではありません。完全にドライな研究室であることから、共同研究相手のところには実験前から入り込んで入念にデザインしてからデータを取得し、数理モデルを作ります。そしてシミュレーションを行うと網羅的にデータを生成できるのでデータドリブン型のアプローチも可能になり、ヒューリスティックに重要な指標を見つけられるようになると考えています。このようにして背後にある非線形動的システムへアタックしています。C型肝炎の治療薬の併剤療法の最適化の事例や、最先端計測技術と数理モデル型アプローチの融合としてHTLV-1という感染症を対象とした事例の紹介がありました。

岩見真吾先生
最後にパネラーの方々によるディスカッションが行われました。川上先生からは、高次元の時系列のデータがあるが、タイムポイントが全員違うときに特徴量を抽出する際は、一回数理モデルを介することが良いのではないか、またその数理モデルが絶対的に正しい必要はなく、いくつか考えられるモデルに当てはめ、そのパラメータを特徴量として使えるのではないかとコメントがありました。垣見先生からは、質の高いデータが必要だが、社会全体でデータの蓄積をサポートすることが大事だ、とコメントありました。岩見先生は、研究レベルで終わってしまっては意味がないので社会実装を進めていきたい、また若い人も是非数理科学の分野に飛び込んできてほしいと訴えられました。合原先生は、数理モデルと機械学習を繋ぐのはすごく強力だが、汎用性のある数理モデルが作れるかにかかっているとのコメントがありました。

桜田先生からは、本日は多面的に議論させて頂いて、新しい医学の可能性を感じることができました。臨床医のもっている直感的な知識体系を数学に置き換えることが重要で、そのためには異分野の人が課題を共有しながら一緒に研究できることが、これからの大きな突破口になると思います、とまとめられ、閉会となりました。
(参考) シンポジウム開催告知


